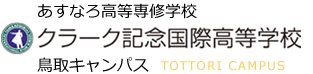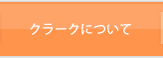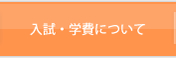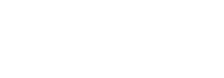学校評価
令和5年度 一般公開資料(自己評価表)
中長期目標(学校ビジョン)
- 学び直しの場として各学年の段階的な教科指導・生徒指導を確立する
- 生徒が本校の所属意識をしっかりと持ち、他者を大切にする心を育む
- 誰一人取り残さない学校にするための対策をする
- 生徒の希望をかなえる進路教育を充実する
- 新しい学びの場としての学校のあり方を模索し、実行する
令和5年度の 重点目標
- 学びなおしを軸とした学ぶ意欲の育成と自ら学習計画を立て実行する力が身につく授業を行う
- クラスの所属意識を持ち安心できるクラス運営
- 登校安定のための生徒支援の評価と共有の徹底
- 進路実現に向けたカリキュラム作成
- 心理的安全性のある環境作り
| 令和5年度当初 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価項目 | 具体目標 | 具体的な取組 | 評価基準・目標 | ||
| 重点目標1に対応 | 学習支援 | 学習意欲向上と学びなおしのための授業工夫 | 生徒が「なるほど!」と感じる授業展開 | 報告課題にとらわれない、社会に繋と繋がる授業展開の工夫 | 授業アンケートの項目「授業中に1回は「なるほど!」と感じることができましたか?」の評価が、5段階で平均4.0以上 |
| 1・2年:基礎学力定着と達成感を得て目標を決めて学ぶことのできる力を養う | 1・2年:進度別学習で数学と英語において中学校3年生までの復習を映像とワークを取り入れながら学び、評価テストと評価表で達成度を確認できるようにする | 進度別アンケートによる授業評価において「授業満足度」の評価が5段階で平均4.0以上 | |||
| 3年:自分の進路に対して必要な学習を選択し進路実現、目標に向かう力を養う | 3年:進度別学習で一般知識のワークと数学と英語の対面授業を中心に自分の進路にあった学びを行う | 進度別アンケートによる授業評価において「授業満足度」の評価が5段階で平均4.0以上 | |||
| 重点目標2に対応 | クラス環境 | 心理的安全性のあるクラス運営 | 自クラスの所属意識を持ち、様々なことにチャレンジできるクラス運営 | 率先して声掛けをするなど相談しやすい環境とクラスの一員と感じれるクラス運営 | クラスアンケートの項目「安心できる、過ごしやすいクラスでしたか。」の評価が5段階で平均4.0以上 |
| 重点目標3に対応 | 登校支援 | 昨年度に引き続き、登校安定に向けたサポートの検討と実践と保護者との情報共有 | 生徒・保護者の情報等から登校しにくい理由を分析し、登校につながる方策を具体化し、段階的に安定した登校へ結びつける | 本人・保護者にあったアプローチと面談の工夫 | 全校生徒の登校率85%以上 |
| 保護者が相談しやすい関わりを持つ | 保護者への連絡方法を工夫して、情報共有を行う | 保護者の学校満足度が評価が5段階で平均4.0以上 | |||
| 生徒情報を共有と支援策の充実 | 学年会の議事録と指導計画の作成と非常勤講師への共通理解 | 朝礼で生徒情報共有の時間を作り、スプレットシート等活用し、非常勤の先生にも情報が確認しやすい環境を作る | 常勤教職員の学年会と生徒会議の満足度が5段階で平均4.0以上 | ||
| 情報分析は担任及び生徒指導担当の教員が行い、分析結果をもとに支援計画書を作成し、評価と修正を定期的に行う | 保護者アンケートの「専門機関等関係者会議を開催したご家庭に質問。関係者会議の満足度は?」の評価が5段階で平均4.0以上 | ||||
| 重点目標4に対応 | 進路実現 | 自分を理解するとともに生き方を発見することで進路実現を援助する | 1年次で自己理解を深め、2年次で方向性を決め、3年次で進路実現を目標とした計画を実施 | 本校の育てたい資質をベースにした特色のある授業(キャリアスタディ・KT)の計画と実践(卒業生講演・企業との関わり等) | キャリアスタディ・KTの満足度の評価が5段階で平均4.0以上 |
| 3年生の生徒・保護者進路アンケートの評価が5段階で平均4.0以上 | |||||
| 進路決定率100% | |||||
| 教員が行っている進路指導・相談内容を保護者へ共有の徹底 | 進路の保護者アンケート各項目の平均が5段階で平均4.0以上 | ||||
| 重点目標5に対応 | 教員の行動原則実行 | 教職員の共通理解のもと、組織として心理的安全性のある学校運営を行う | 教員行動原則の実行 |
|
自己評価アンケート各項目の評価が5段階で平均4.0以上 |
| 他者評価アンケー(対職員・対主幹教諭)ト各項目の評価が5段階で平均4.0以上 | |||||
| 評価結果:令和6年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価項目 | 経過・達成状況 | 評価 | 自己評価・次年度課題 | ||
| 重点目標1に対応 | 学習支援 | 学びなおしのための授業工夫 | 全ての授業の平均は4.3であった。各学年は1年生が4.6、2年生が4.2、3年生4.1であった。 | A | 目標を達成し、特に1年生で高評価を得たことは良かったが、今後の課題として、3年生の評価を更に向上させるため、より興味を引く社会との繋がりを強化した授業展開の工夫が必要である。 |
| 全体のアンケートの結果は、4.0であった。各学年では、1年生が4.2、2年生が3.7であった。 | A | 全体の授業満足度は目標の平均4.0を達成したが、1年生と2年生で評価に差が見られた。1年生は目標を上回る4.2で満足度が高い一方、2年生は3.7とやや低めである。次年度課題として、2年生の満足度向上のため、進度や教材の見直し、個別サポートの充実を図る。また、フィードバックを活用して授業改善に努める。 | |||
| 3年生の授業アンケートは3.4であった。 | B | 3年生の授業満足度は3.4と目標の平均4.0を下回った。進度別学習や進路に合った学びが十分に効果を発揮できなかったと感じる。課題として、3年生の満足度向上のため、進路に応じた授業内容の再検討や個別サポートの強化が必要である。生徒のニーズをより反映した授業改善に努める。 | |||
| 重点目標2に対応 | クラス環境 | 心理的安全性のあるクラス運営 | 全体のアンケートは4.1であった。各学年は1年生が4.4、2年生が3.7、3年生4.2であった。 | A | 全体のクラス満足度は4.1で目標を達成したが、2年生の評価が3.7と低いことが課題である。1年生と3年生は高評価であった。課題として、安心感向上のため、教員の声掛けやサポートを強化し、より相談しやすい環境づくりに努める。また、クラス活動の充実も検討する。 |
| 重点目標3に対応 | 登校支援 | 昨年度に引き続き、登校安定に向けたサポートの検討と実践と保護者との情報共有 | 全校生徒の登校率は、86%であり、各学年は1年生が81%、2年生が88%、3年生91%であった。 | A | 全校生徒の登校率は86%で目標を達成したが、1年生の登校率が81%と低かった。2年生と3年生は目標を上回った。課題として、1年生の登校率向上のため、個別のサポートと面談の強化が必要である。保護者との連携を密にし、登校しやすい環境をさらに整備する。 |
| 全体の満足度のアンケートは4.4であった。各学年は1年生が4.5、2年生が4.3、3年生4.3であった。 | A | 自己評価としては、目標を達成し、保護者への働きかけの工夫が効果的であったと考える。全体の満足度が平均4.4を達成し、各学年も満足度が高い結果となった。しかし、保護者の多様なニーズに対応するために、今後も継続的な改善が必要である。 | |||
| 生徒情報を共有と支援策の充実 | 全学年の学年会満足度は3.8であった。特に「学年会で指導計画を作成する生徒についての検討ができたか?」が2.8と低かった。 | B | 自己評価としては、全体の満足度が目標に届かず、特に指導計画に関する検討が不十分であったと考える。今後は、情報共有の方法や内容を見直し、非常勤講師を含めた連携強化が必要である。 | ||
| 関係者会議を行ったご家庭の全体の満足度は4.2であった。 | A | 関係者会議を行った家庭の満足度は4.2で、目標を上回った。課題として、全体の評価をさらに向上させるため、情報共有と支援策の改善が必要である。 | |||
| 重点目標4に対応 | 進路実現 | 自分を理解するとともに生き方を発見することで進路実現を援助する | キャリアスタディの全体の満足度は4.0であり、1年生が4.4、2年生が3.7、3年生が3.6であった。またKTの全体の満足度は4.3であり、1年生が4.5、2年生が3.9、3年生が4.4であった。 | A | キャリアスタディの全体満足度は目標の4.0を達成したが、2・3年生の満足度が低い。課題として、学年別に満足度のばらつきを減らすための改善が必要である。 |
| 保護者のアンケートの平均は、4.3であった。生徒のアンケートの平均は、4.4であった。 | A | 保護者の満足度は4.3、生徒の満足度は4.4で目標を達成した。課題として、さらなる満足度向上のために、情報提供と進路支援の強化が必要である。 | |||
| 43名のうち、39名(91%)の進路が決定した。 | A | 進路決定率は91%に留まり、目標の100%に達しなかった。課題として、進路を考えることが中々できない生徒や未決定者への個別支援強化と、進路情報提供の充実が必要である。 | |||
| 保護者の進路に関するアンケートで、「担任・担当・学年担当と、お子様の進路情報の共有は十分にできましたか?」のアンケート平均は4.3であった。 | A | 進路情報の保護者共有に関するアンケートの平均は4.3で、目標を達成した。課題として、さらなる共有の徹底と個別対応の強化が必要である。 | |||
| 重点目標5に対応 | 教員の行動原則実行 | 教職員の共通理解のもと、組織として心理的安全性のある学校運営を行う | 教員の行動原則自己評価アンケートでは、全体の平均が3.7であった。 | B | 教員の行動原則自己評価アンケートの平均は3.7で目標に達しなかった。特に情報共有と書類の事前提出に課題があり、改善が必要である。課題として、これらの点を重点的に強化することが必要である。 |
| 主幹教諭から常勤教諭へのアンケート平均は、3.6であり、常勤教諭から主幹教諭へのアンケート平均は4.3であった。質問内容は、それぞれ違うが全体の平均は3.9であった。 | B | 主幹教諭からの評価平均は3.6で目標の4.0に達しなかったが、常勤教諭からの評価は4.3で高評価だった。全体平均は3.9であり、均衡を保つためにさらなる改善が必要である。課題として、常勤教諭への支援強化と質問内容の調整を行う。 | |||
【 評価基準 】
A:十分達成 [目標に対して80%以上]・[目標に対して4.0以上]
B:概ね達成 [目標に対して60%以上]・[目標に対して3.0以上]
C:変化の兆し [目標に対して40%以上]・[目標に対して2.0以上]
D:不十分 [目標に対して40%未満]・[目標に対して2.0未満]
令和6年度 一般公開資料(自己評価表)
中長期目標(学校ビジョン)
- 学び直しの場として各学年の段階的な教科指導・生徒指導を確立する
- 生徒が本校の所属意識をしっかりと持ち、他者を大切にする心を育む
- 誰一人取り残さない学校にするための対策をする
- 生徒の希望をかなえるキャリア教育を充実する
- 高等専修学校としての学校のあり方を模索し、実行する
今年度の 重点目標
- 基礎学力の定着と思考力・判断力・表現力を身につける授業展開を積極的に行う
- 主体性・協働性・多様性を身につけることを目指したクラス運営・授業・学校行事を積極的に行う
- 傾聴と対話を中心とした生徒の関わりと安心と安全の学校環境づくりを行う
- 多種多様な進路選択を実現できる環境作りとキャリア教育の見直し・3年間計画の作成を行う
- 仕事の整理と仕組み化の構築と共通理解を行う
- 地域と繋がり教科横断を含め職業教育を取り入れた授業展開を行う
| 令和6年度当初 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価項目 | 主要目標 | 細分目標 | 具体的な取組 | 評価基準・目標 | |
| 重点目標1に対応 | キャリア教育 | 基礎学力の定着 | 個々の基礎学力向上を目指したシステム構築を行う。 | 進度別学習において個別最適化したコース学習を実施し、その中で動画を活用した学習・個別学習を行う。 | 進度別学習の課題点・取り組み点B以上が80%以上。 |
| 令和7年度以降の進度別学習で実施する国語のシラバスを作成する。 | 人文学・演劇教育・対話的な活動を活用しながら、言語活動を通して文部科学省で定められている「聞く・話す・読む・書く」の力を伸ばす内容を取り入れる。 | シラバスが完成している。 | |||
| 教務 | 思考力・判断力・表現力を身につける授業展開 | 一般科目でPBL学習または探究学習を取り入れた内容を行う。 | テーマを設定し、問題提起を通して問題を調査し、データを分析する。 その調査・分析から解決策や計画を提案し、成果を発表・振り返りを行うことで今後の改善点を考える。 |
年度内の実施率80%以上。 | |
| 重点目標2に対応 | 教務 | 主体性・協働性・多様性を身につけることを目指した学校行事 | 主体性・協働性・多様性を目的とした行事立案と生徒への周知と振り返りが充実した学校行事の運営を行う。 | 主体性(生徒のアイデアを募集し、自ら行事を企画・立案できる機会を提供する)、協働性(生徒同士や教職員との協力を促進するために、異なる学年やクラスが協力して行事を企画・実施する)、多様性(多様な生徒が参加しやすい行事を企画・実施する)を目的とした行事を実施する。 | 行事後に実施する生徒アンケートで「行事の目的が達成できた」の回答が5段階評価で平均4.0以上。 |
| キャリア教育・生徒指導 | 主体性・協働性・多様性を身につけることを目指したクラス運営 | R7年度以降のために、主体性・協働性・多様性を身につけるためのLHRカリキュラムの再構築を行う。 | 主体性、協働性、多様性をテーマに自己理解と他者理解のワークショップ、社会貢献活動の企画・実施するLHRを年間カリキュラムに取り込む。また、LHRの活動に対してフィードバックセッションやアンケート調査などを通して生徒と教員が相互にフィードバックを行うシステムを構築する。 | カリキュラムが完成する。 | |
| 重点目標3に対応 | 教務 | 生徒・保護者ともに傾聴と対話を中心とした関わりのための安心と安全の学校環境つくり | 各教室の有効利用と安心安全の環境作りを実施する。 | 教室の最適活用:学年クラスの配置と備品を最適化する。 安心安全な環境:防犯設備の設置と緊急対応体制を整備する。 教室の清潔と整備:定期清掃と設備修理の迅速対応。 |
学期末に実施するアンケートで「安心安全」との回答が5段階評価で平均4.0以上。 |
| R7年度に向けて合理的配慮の検討を行い計画の作成をする。 |
|
合理的配慮の計画が完成した。 | |||
| 生徒指導 | チーム担任制の充実により教職員が全生徒を支える仕組みをつくる。 | 1人の生徒を複数の教員が担任することで多面的な視点を持って関わり、また多様な価値観に触れる機会を増やす中で、生徒の自律心・主体性を育む。 | 育てたい資質について学期末に生徒に対してアンケートを実施し、自律心(自己決定力)・主体性(セルフマネジメント)育成の成果についての項目で5段階評価で平均4.0以上。 | ||
| 傾聴と対話を重ねていく中で生徒が安心して過ごせる学校・クラスを、そして保護者も安心して相談できる環境をつくる。 | 毎日の情報共有をルーティン化することで、全教員が同じ情報を共有し、生徒・保護者の支援指導に活かす仕組みを確立する。 | 学期末に保護者対象の評価アンケートを実施し、5段階評価で平均4.0以上。 | |||
| 重点目標4に対応 | キャリア教育・生徒指導 | 傾聴と対話をベースに進路実現に向けた情報共有と進路指導を行う | 生徒にとって後悔のない進路選択を実現するために段階的に以下の目標を掲げる。
|
進路選択に際して、本人と保護者が納得のいく進路を実現できるよう以下の項目に対して情報提供・助言をしていく。
|
生徒対象の進路指導に対する満足度アンケートを実施し、評価4.0以上。 |
| 各家庭の進路に対する方針も考慮しつつ、保護者との連携を密にとることで情報共有を徹底する。 | 進路に向かう意識に相違がないようにコミュニケーションを徹底する。 | 保護者対象の進路指導に対する満足度アンケートを実施し、評価4.0以上。 | |||
| キャリア教育・教務 | 多種多様な進路選択を実現できる3年間進路計画の作成 | 令和7年度以降のLHR・キャリアスタディと連携した進路計画の作成を行う。 | LHRやキャリアスタディの中で、進路選択セミナー、大学・専門学校の説明会、職業体験プログラムなど、多様な進路選択の情報を提供する。また、卒業生の進路情報を収集し、具体的な進路イメージを持たせるカリキュラム作りを行う。 | 進路計画が完成する。 | |
| 自分とは違う文化や習慣、考え方、価値観ついて考える。 | 外国籍の方等と関わる授業を取り入れ、様々な考え方を学ぶ機会を提供する。 | 授業後のアンケートで「様々な考え方を知ることができた」の回答が5段階で4.0以上。 | |||
| 重点目標5に対応 | 教務 | 仕事の整理と仕組み化 | スケジュール管理とフォームの統一。 | Googleworkspaceを活用し、分掌ごとのスケジュール管理を徹底させる。 | 分掌ごとのスケジュールが完成できた。 |
| 情報共有とワークフローの統一 | Googleworkspaceを活用し、教職員間の情報共有を行う。ファイルの作成や保存ルールを設け、誰がどの分掌や担当になっても困らない環境作りに取り組む。 | 教職員アンケートで情報共有できたとの回答が4.0以上 ファイル作成や保存ルールができた。 |
|||
| 入試・広報 | スムーズな入試行事を行う | 各入試行事の早めのスケジュール提案と時間設定を行う。 | 入試担当者で役割を決め、各項目に締切を設け、スケジュール管理を行う。また、教職員が入試行事の概要が把握しやすいよう、随時情報を更新していく。 | 行事前のミーティングと行事後の振り返りを毎回実施できた。 | |
| 入試行事の充実。 | 行事日程・内容・手順等を教職員で情報共有することで、受験者(参加者)の活動サポートを全教員でできる体制を構築する。 | 全教職員間で情報共有ができ、出願者数が令和5年度入試と比較して5%増加。 | |||
| 重点目標6に対応 | キャリア教育 | 職業教育を取り入れた授業展開、学校行事を行う | 学校行事、専修学校設定科目の中で、職業教育の活動や授業展開を行う。 | 学校行事では、職業教育としてお金の取り扱いなど取り入れたイベント企画をする。専修学校設定科目の中で、企業や地域との連携による実践的な学習機会を設け、情報社会の中で生き抜くパソコンスキルを身につける授業展開を行う。 | 各行事や授業で職業教育についてのアンケートを実施し、各項目で5段階評価で平均4.0以上。.0以上 |
| 入試・広報 | 地域と関わる行事を計画し実施する | クラークフリースクールの実施。 | 鳥取県内の不登校、相談室登校、及び引きこもりの小中学生に対して学校への復帰並びに健康的な生活へのきっかけ作りなどの教育支援を行う。 | 参加児童生徒のアンケート項目、「参加してよかった」の回答が5段階評価で平均4.0以上。 | |
| 教育支援センター『すてっぷ』との連携。 | 学校行事に『すてっぷ』の児童生徒が参加する企画を取り入れる。 | 企画・実施できたかどうか。 | |||
| 受験者が本校についての理解を深め、入学への意欲を高められる生徒募集・入試行事の立案・実施。 | 複数の媒体を使い、本校の取り組みを伝える活動を行うとともに、生徒募集行事の参加者が本校の魅力を感じる内容を検討して、実施をする。 |
|
|||
【 評価基準 】
A:十分達成 [目標に対して80%以上]・[目標に対して4.0以上]
B:概ね達成 [目標に対して60%以上]・[目標に対して3.0以上]
C:変化の兆し [目標に対して40%以上]・[目標に対して2.0以上]
D:不十分 [目標に対して40%未満]・[目標に対して2.0未満]